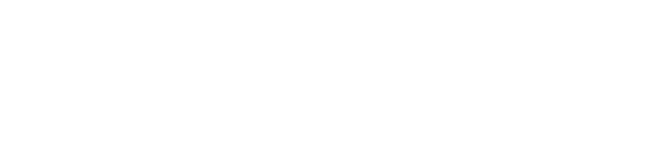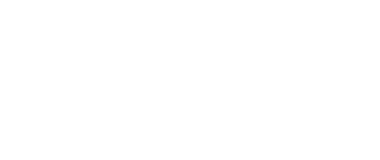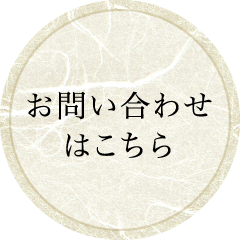お知らせ
- トップページ
- >
- 善宗寺からのお知らせ
- >
- 葬儀における数珠の持ち方や使い方について

葬儀や通夜などに参列するとき、一般的に数珠を持参します。数珠の種類は大きく二つに分けられます。一つ目は各宗派の正式な数珠である「本式数珠」、二つ目はどの宗派でもお使い頂ける「略式数珠」です。
基本的には自宅にある数珠をお持ち頂ければ問題ありません。数珠が自宅にない場合、特に宗派のこだわりが無ければ略式数珠を一つ購入しておくと便利です。
今回のコラムでは、葬儀や通夜の必需品とも言える数珠の持ち方や使い方について紹介していきます。
数珠の持ち方・使い方
数珠は基本的に左手にかけて使います。仏教において、右手は清浄な手・左手は不浄な手という考え方があり、不浄を浄化するために数珠は左手にかけるものとされています。
数珠は座っているときは左手首にかけておき、立っているときや移動のときなどは房を下にして左手で持ち歩くのが一般的なマナーです。
次に数珠の使い方について説明していきます。数珠を使用するのは、僧侶がお経を唱えているときやお焼香のときなど、仏様に合掌をするときです。
合掌をする際、数珠は左手の親指と人差し指の間にかけます。そしてそのまま右手を左手に合わせ、指先をきちんと揃えて角度は45度ほどになるようにしましょう。合掌した両手は胸元のあたりに置き、背筋を伸ばします。これが美しい合掌の姿勢です。
また、宗派によっては両手に数珠を通して合掌をする場合もあります。どちらが正しいということでもありませんが、気になる場合はご自身の宗派の作法に合わせるのが良いでしょう。
なぜ葬儀に数珠を持参するのか

数珠の起源については諸説ありますが、もともとは古代インドのバラモン教で用いられていた道具が原型となっており、それをお釈迦様が仏教に取り入れたという説が最も有力です。
数珠の珠数は108つを基本としています。108というのは人間の煩悩の数です。もともと数珠は、お経を唱えた数を数えるために使われていました。 なので「珠を数える」と書いて「数珠」なのです。
古来より数珠の珠には厄除けやお守りの力があると考えられていたため、念仏を唱えるごとに数珠を通して人間のあらゆる煩悩を退散させていたのです。また、数珠は「念珠」と呼ばれることもあります。
このように、数珠の珠数が108つだというのは非常に重要なことでした。しかし、数珠の文化が一般に浸透した現代では略式数珠を持つ人が多くなり、108の約数である54、36、27、18珠の数珠が増えてきています。なのでお持ちの数珠の珠数が108でないからといって正式な数珠ではないということではありませんので、安心してください。
数珠は煩悩を消して心身を清める役割を持っています。そのため、葬儀や通夜など故人へ手を合わせるとき、清浄な心で弔いをするために数珠は必要なものなのです。