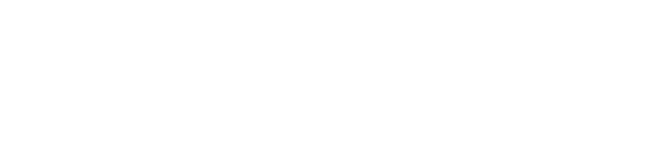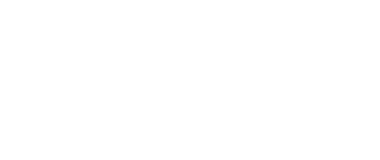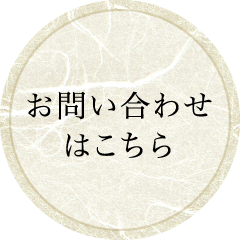お知らせ
- トップページ
- >
- 善宗寺からのお知らせ
- >
- お悔やみの言葉|正しい伝え方を知ろう

「悔やみ」とは、故人の死を悼み、残された遺族などにかける慰めの言葉のことです。訃報を受けた際にはお悔やみの言葉を申し上げるのが一般的なマナーです。
ではお悔やみの言葉は、いつどのようなタイミングでどのような言葉をかければ良いものなのでしょうか?今回のコラムではお悔やみの言葉の正しい伝え方について解説をしていきます。
お悔やみの言葉
お悔やみには必要以上のことは言わず、簡素に伝えるのが大切です。心を込めて伝えれば短い言葉でも気持ちは十分に伝わります。
◆一般的なお悔やみの言葉
「この度はご愁傷様です」
「心よりお悔やみ申し上げます」
「哀悼の意を表します」
「○○様のご冥福をお祈り申し上げます」※
「お力落としのことと思いますが、どうかご自愛ください」
一般的なお悔やみの言葉は上記の通りです。長々と話すのは迷惑となりますので、短く伝えるよう心掛けてください。
なお宗教によっては「※ご冥福」という言葉が適切でない場合があります。「冥福を祈る」というのは「死後の幸福を祈る」という意味です。浄土真宗やキリスト教などでは死後の考え方が他の宗派とは異なるため、基本的に「冥福を祈る」という言葉は使いません。
また、葬儀では使ってはいけない「忌み言葉」がありますので、そちらも気を付けましょう。
◆葬儀でタブーとされる言葉
・「度々」「重ね重ね」「再三」などの重ね言葉⇒不幸が重なるとしてNG
・「死ぬ」「死去」など直接的な死の表現⇒「生前」「ご逝去」などに言い換える
・「四」「九」などの縁起の悪い言葉⇒「死」や「苦しみ」を連想するためNG
・死因を直接尋ねるような言葉
お悔やみの言葉を伝えるタイミング

お悔やみの言葉を伝えるタイミングはいくつかあります。
まず遺族の方から電話やメールなどで訃報の連絡を受けた際、お悔やみの言葉を伝えます。遺族の方は悲しみの中で連絡をしてくださっているはずですので、言葉を選んで慎重に話しましょう。
次に通夜や葬儀の当日です。葬儀の受付は故人の近しい人が担当をする場合が多いため、そのときは一言お悔やみの言葉をかけるようにしてください。受付には参列者が並んでいるため簡潔に伝えましょう。
お悔やみの言葉を伝えるタイミングはあまり多くはありませんが、葬儀に参列した際にはできるだけお悔やみの言葉を伝えるようにしてください。
葬儀・通夜に参加できず弔電でお悔やみの言葉を伝える場合は、訃報を聞いたらすぐに用意し通夜に届けられるようにしましょう。