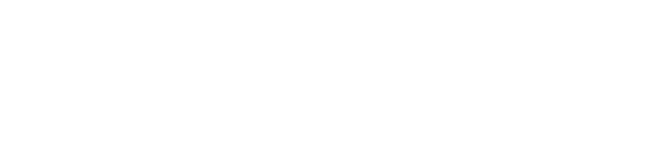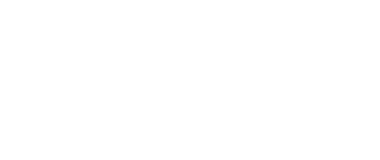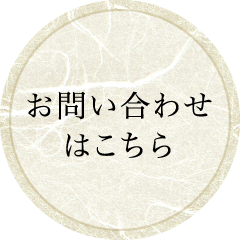お知らせ
- トップページ
- >
- 善宗寺からのお知らせ
- >
- 葬儀後の納骨はいつにするのが正しい?

葬儀で火葬が終わった後、遺骨は骨壺に納めて遺族が引き取るのが一般的です。引き取った後の遺骨をお墓に納めることを「納骨」といいます。
では、納骨の時期は葬儀後いつにするのが正しいものなのでしょうか?今回のコラムでは納骨の時期についてまとめていきます。
納骨の時期
まず、基本的に納骨の時期について「絶対にいつまでに行わなければならない」といった決まりはありません。遺骨を引き取った人の都合の良いタイミングでしてもらえれば大丈夫です。
ただし、一般的には葬儀後の法要のタイミングで納骨を行う人が多いようです。具体的には「四十九日」や「百か日法要」や「一周忌」などです。特に四十九日は仏教において忌明けとされているため、一つの区切りとして四十九日に納骨をする人が最も多いそうです。
しかし四十九日では納骨をするお墓などがまだ決まっていないケースがあります。その場合は百か日法要や一周忌などを目安に、ある程度気持ちが落ち着いてから納骨をしましょう。
このように、納骨は「目安となる時期」はありますが、「絶対にしなければならない時期」はありません。法要など遺族が集まる機会に納骨式を行うのが一般的とされています。
納骨の場所

昔は遺骨は墓に納めるのが一般的でした。しかし近年では墓を持たない家庭が増え、納骨をする場所が選べる時代になってきています。納骨の場所をいくつか紹介します。
・霊園、墓地
最も一般的なのが、墓地や霊園の一部の土地を買い取り、そこにお墓を建てる方法です。基本的に墓は家族代々で利用することができ、また花を供えたり目の前で手を合わせたり伝統的なお墓参りをすることができます。
ただ墓を建てるには平均200万円ほどの費用が掛かることや、定期的に手入れをしなくてはならないことなど、お金や手間が掛かってしまうのも事実です。
・納骨堂
近年で増加傾向にあるのが納骨堂に遺骨を納める方法です。安価で済み、建物の中で大切に保管してもらえるので安心感があります。屋内なので手入れも必要ありません。
納骨堂はロッカーのような場所になるため、日本の伝統文化のようなものは感じられず、好みは別れるかもしれません。
・自宅保管
納骨堂に次いで増えているのが自宅で遺骨を保管するケースです。遺骨が入った骨壺は仏間や仏壇に置くのが一番自然です。
仏壇が無ければ、部屋のどこかに骨壺や遺影を置く供養スペースを設けると良いでしょう。インテリアに合わせたデザインの骨壺を選べば、リビングなどにも自然に骨壺を置いておくことが可能です。
他には散骨をするケースや、合同墓に納骨をする方法、樹木葬などの方法があります。どれが正しいということではありませんので、家族間でよく相談して納骨の方法を決めてください。
なお 善宗寺では、四十九日(満中陰)後の納骨を受け付けています。宗旨や宗派は問いません。 詳しいことはこちらをご覧くださいませ。